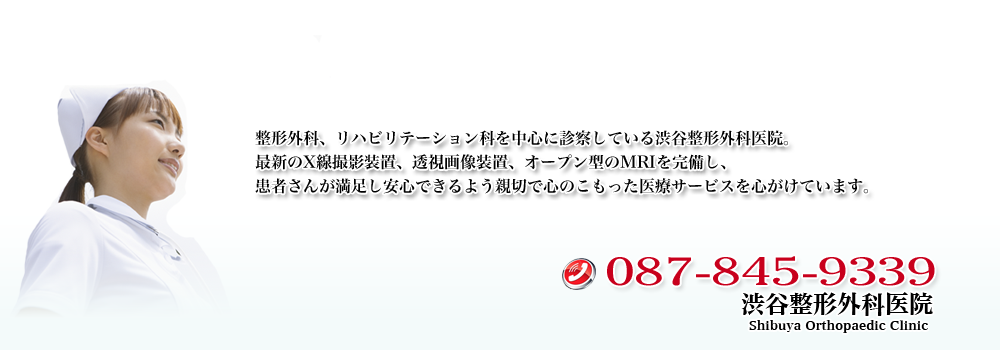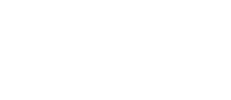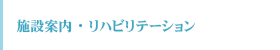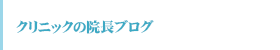頚椎症性脊髄症について
頚椎には、椎体の変形、脊柱配列の微妙なズレ、椎間板高の減少などが、主に年齢的な変化として
生じてきますが、これを「変形性頚椎症」といいます。このこと自体は病気というより加齢的、生理的
変化であって誰にでも起こってきます。
しかし、一部の方ではこれらの頚椎症変化が基盤となって、内部を走行する脊髄神経組織を障害し、
様々な症状を引き起こします。特に脊髄そのものが圧迫障害を受けて脊髄麻痺症状を慢性的な経過で
生じてくる場合に、「頚椎症性脊髄症」と呼ばれ、病的な状態と判断されます。
主な症状としては、四肢のしびれ、手のしびれ、手指動作のぎこちなさが目立つようになります。
特に箸が使いにくくなったり、ボタンかけ、字を書いたりが、以前のように上手にできないと言われます。
高齢の方が発症することが多いので年のせいと勘違いされてしまうこともあるようです。
下肢症状としては、足底部のしびれ、立位、歩行時の不安定感が強く、歩行が大変ぎこちなく感じるようになります。
基本的な経過は数か月〜年単位で徐々に進行する慢性疾患と言えますが、一部の高齢者の患者さん
では、週単位で急速に症状が進行し、強い運動機能麻痺を生じることがあります。
そのため脳血管疾患(脳卒中)と間違うような経過を取られる方もいます。上記の症状に該当しつつ、
神経内科、脳血管外科などで異常がないと言われた方は、是非お早めにご相談ください。
治療においては、脊髄障害の程度を神経学的な診察を正確に行って判断することが重要になります。
画像検査による診断では、単純X線撮影、MRI、脊髄造影CTなどで頚椎の状態、脊髄圧迫状態が
非常に明瞭に把握できますが、必ずしも症状が重症でない方もおられます。
症状が四肢のしびれ感などが主体で、運動機能自体の低下がなく、日常生活動作にも支障がない
レベルであれば、慎重な経過観察でよいだろうと考えています。
これまでの経験でも他院で手術を強く勧められたが、迷っているという方には、このような患者さん
が多いように思います。
また、手術を受けたものの術後経過に納得がいかないため、診察を受けに来られた患者さんも
時折見かけることがあります。
実際の手術治療ですが、私は過去10年以上にわたって片開き式椎弓形成術を行ってきました。
従来は一律に第3から第7頚椎レベルまでの5椎弓をすべて拡大させる方法を行っていましたが、
ここ5年ほど前からは、脊髄の圧迫状態に応じて拡大範囲を限定した術式に変更しています。
そのため、手術切開範囲も小さく、出血量も100ml未満で済むことも多く、輸血を要することは
まずなくなりました。また私が医師になりたての頃には、肉眼レベルで手術を行うのが全く
普通のことでしたが、現在は拡大鏡(手術用ルーペ)または顕微鏡を使用して、より繊細な
手術操作を行うようになっています。
これにより、10年以上前に解析した椎弓形成術の手術例では、約7%程度あった術後の肩の
拳上障害は、2〜3%未満まで低下しています。
また重大な合併症は認めておらず、安定した手術方法であると感じています
この「頚椎症性脊髄症」は院長である私が、整形外科医として、また脊椎専門外科医として
特に力を入れて取り組んできた疾患の一つです。
診断、治療の方針、手術方法の選択、術後の症状改善の予想、中長期的なチェックポイント
などについては、これまでの多くの経験、臨床的データに基づいた説明を行います。
是非ご相談ください。
この文書の著作権は医療法人社団渋谷整形外科医院に属しています。
この文章の無断転載、複写等はご遠慮下さい。
Copyright c Shibuya Orthopaedic Clinic All Rights Reserved